今日も患者さんへの看護ケア、お仕事お疲れ様です
あなたの働きはきっとケアした方の助けになっています
あなたの頑張りや辛さはあなたの力になっています
今日を過ごせた自分をよく頑張ったと認めましょう
こんにちは!
今回は観察の最後、全身評価について学習していきましょう!
具体的な観察項目は「体温と皮膚」です!

本日の結論!!
・急変を防ぐ観察として全身観察として「体温・皮膚」をみるコツがわかる!
・発熱した場合の対応と推奨されないクーリングについて知ることができる!
・皮膚の観察のポイントがわかります!

体温は毎日測っているからすぐに実践できるよ!皮膚って言われても色々な意味があるような気がする・・・

そうだね!体温のこともすごく大切だから再確認することと、皮膚って色々な病気や状態で変わるけど、今回は急変を防ぐ観察で必要な皮膚の観察を教えてるね。
それでは学習していこ〜
<もくじ>
1.体温を測定しよう
2.要注意以上の発熱は対応を!
3.発熱はクーリングはする必要があるのか
4.皮膚の状態を観察
4.1.外傷の確認をしよう!
4.2.紅斑も確認しよう
4.3.点状出血と紫斑
5.私の経験した症例
6.まとめ
1.体温を測定しよう
体温は体温計で測定しましょう
集中治療室や救急救命センター等で働いていると中枢温(膀胱温や直腸温など)を測定していることがありますが、今回は皮膚温について話していきます
私の行動基準の異常値
警戒(微熱、3時間以内に再検)37.5〜37.9度
要注意(高熱、報告and指示に従った対応)38.0〜38.9度
即行動(報告と迅速な指示に従った対応)39.0度 以上
2.要注意以上の発熱は対応を!
要注意以上の体温が出た場合は、解熱剤や追加の検査が必要になります
熱が出てたらとにかく解熱剤を使用すればいいわけではないです
熱が出ている原因がどこにあるか考える必要があります
入院中の患者さんが急に発熱を起こす原因のTOP3
①肺炎
②尿路感染症
③腸炎
さらに、発熱している原因を治療しないといつまでも熱が続き、患者さんが苦しむことになります
新規に発熱したり、発熱が続く場合はまず、これらの可能性を考えて医師に報告する必要があります
一般的な検査として以下を行うことが多いです
これを抑えておくことで、先輩や医師からの次に出される指示を予測することができるようになります!
入院中の患者さんが急に発熱を起こす原因のTOP3のどれかわからないけど、検査を進める場合
①肺炎 ②尿路感染症 ③腸炎
<3つの検査>
採血・尿・胸部レントゲン
<3つ+αの培養>
血液・尿・痰・(便)
3.発熱はクーリングはする必要があるのか
結論
あまり推奨されません!
私は基本的にはアイスノンや氷嚢によるクーリングをすることはありませんでした
理由として、アイスノンや氷嚢によるクーリングは解熱作用が期待できないからです
よく、表在に大きな動脈を冷やすと冷えるということを聞きますが、その効果は不明瞭です
ただ、次の2つのケースは必要があると考えています
①患者さんが暑くて不快感があるからアイスノンを渡す
②打撲などにより患部の炎症が強い場合はクーリングが必要
ただ、この事実が浸透していなかったり、何かやってあげたいという看護師の愛情でクーリングを積極的に行う看護師がいるのも事実です
患者さんにとって不快や不利益(シバリングや悪寒があるのにクーリングするなど)になっていなければ、ダメということはないと思います
「なんで熱が出てるのに冷やしてないの!?」
と声をかけられることもあるかと思いますが、患者さんの不利益にならない範囲で対応しましょう
4.皮膚の状態を観察
ここで解説している急変を未然に防ぐ観察においる皮膚の外観を確認しましょう
①外傷がないか②紅斑がないか③点状出血③紫斑などを指します
①外傷の確認をしよう!
患者さんの全身の皮膚の観察をしましょう!
断りを入れて、布団を外して足の先まで確認することが望ましいです
自立している方はケースバイケースとなりますが、ベッド上やベッド周りまでの日常生活動作(ADL)でしたら必ず確認しましょう
臥床に伴う褥瘡や医療関連機器褥瘡と呼ばれるMDRPUが発生していることがあります
また、動ける方でもよくよく話を聞くと「さっき棚の物を取ろうとしてふらついて頭をぶっちゃったんだよ〜」ってことがあり、
患者さんの頭に血腫を作っていることも過去に経験していますので私は少し辻まつの合わなさを感じたらよくコミュニケーションをとるようにしています
②紅斑も確認しよう
感染症やアレルギー反応が起きるとほっぺたなどで現れたことを見たことがあります
全身の皮膚に出ることもあります
これは、表皮の毛細血管が拡張することにより起こる現象です
普段はないものなので、皮膚が赤いぞ!!って思ったら何か異常かもしれないと詳しく観察しましょう
③点状出血と紫斑
点状出血は表皮に近い毛細血管が破れることにより起こります
その名の通り「点状」の赤紫色の集団が皮膚で観察できます
血小板減少などによる起こることがあります
紫斑の見た目は点状出血と似てますが、範囲が広いものを指します
5.私の経験した症例
80歳台、男性、心不全による入院、3日目
後輩看護師さんから声をかけられました

SpO2がちょっと低いんですよね〜、深呼吸すれば94%まで上がるんで大丈夫だとは思いますが
気になった私は、ベッドサイドまでいき患者さんに声をかけました

Aさん、調子どうですか〜

だいじょう、、ぶだと思います、、よ

あれ?会話の中で言葉が切れている。言葉の途中で呼吸が入っているかも
観察をABCDEの順番でやると
呼吸数28回/分で体温が38.5度で断続性のラ音がある・・・

あ、肺炎を併発したかもしれない!SpO2は良くてもこのままだと破綻する。すぐ報告して、検査や治療の必要がある!
医師に報告して、血液培養と痰培養を採取して、抗生剤の投与と酸素投与が開始となりました
6.まとめ
いかがでしょうか
今回は体温管理について、主に発熱のことについて触れました
発熱した場合のクーリングは日常的に行われることがありますが、推奨はされていません
必要な報告と予測した早期の検査が重要ですので、知識として蓄えておきましょう
思いがけない皮膚トラブル(実は転倒して怪我していた)もあります
患者さんの皮膚確認も必要だと改めて頭に入れて観察をしていきましょう
以上、しーちゃんでした!
最後まで読んでいただきありがとうございます!
この記事があたなに少しでも役に立っていただけたら幸いです
⭐️この記事を読んでいることが、あなたが頑張っている証拠です!
これからも、少しずつ学んで成長していきましょう⭐️
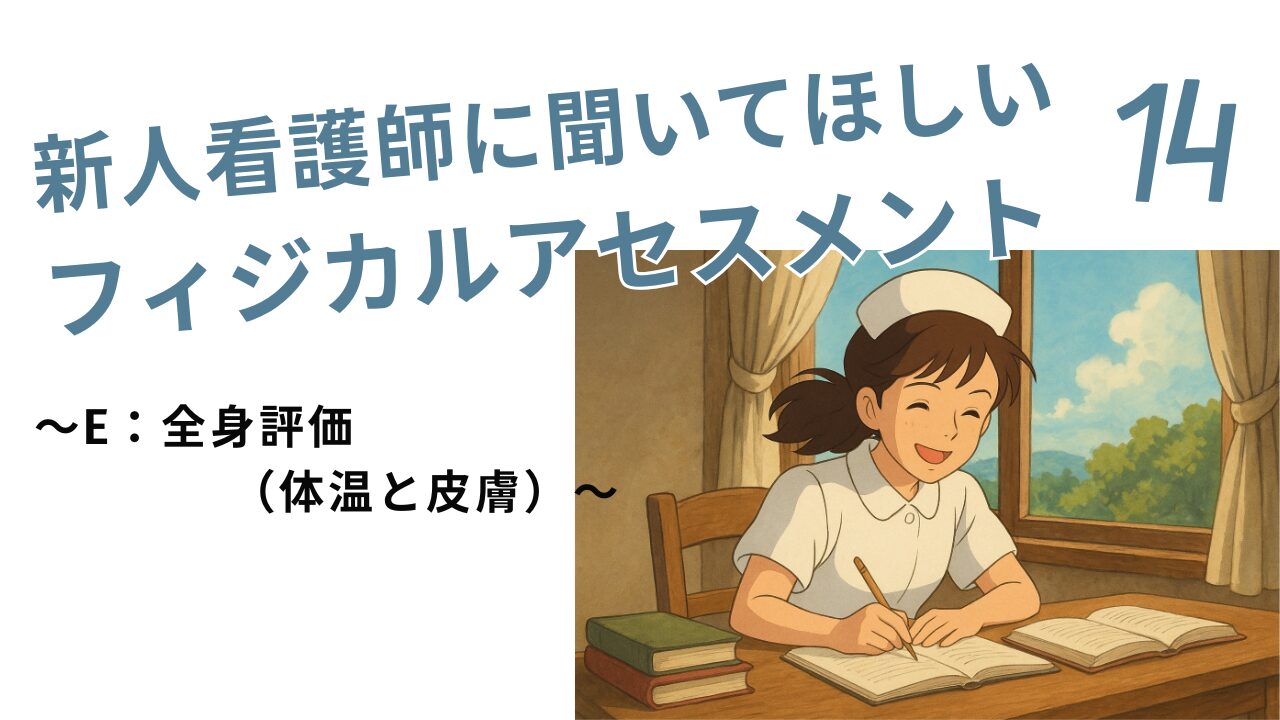

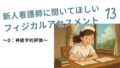
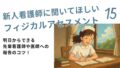
コメント